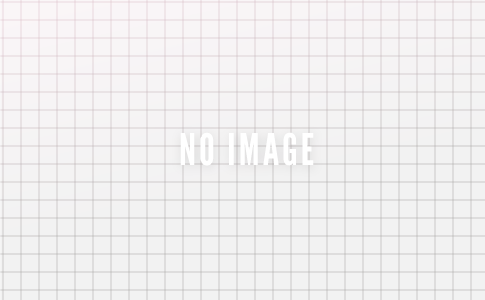筆者は1984年に古川凱章先生が主宰する「順位戦101」に入会を許されました。当時は他にも麻雀団体は存在したのですが、迷いなく101を目指したのです。大きな理由は試合結果の評価がトップから順に「1・0・0・△1」(△はマイナスを表す)と得点を無視することに、激しく賛同していたからです。
実は第1期最高位戦(その当時は団体名ではなく、タイトル戦の名称)を開催するに当たっては評価をどうするかで意見が分かれ、その結果「順位率部門」と「得点部門」の二人の最高位が誕生したのでした。
ただ、世間で順位のみを競って麻雀を打っている人はほぼ皆無といって良く、2期目からは得点に順位点をプラスしてポイントに置き換える現在の折衷案に変わりました。
これは筆者の想像ですが、最高位が毎回二人というのも味が悪く、世間の遊び方に寄せて人気を博したいという主催誌(専門誌の「近代麻雀」)の狙いもあったはずです。
101は順位率評価ではありませんが、野球が10対0でも1対0でも1勝は1勝であるように、麻雀も勝ちと負けの評価のみで戦おうという考え方でした。
競技者としての楽しみが最優先
その世間からまったく隔絶した(今はガラパゴス化などと呼ぶ)101をなぜ愛好したかというと、単純にプレイして面白かったからです。
よく人生の最後の一食に何を食べるか問題が語られますが、最後の半荘をどのルール・システムで打つかを考えてみてください。ポイント制の場合、浮けば(プラスなら)満足するのか、プラス50Pなら幸せに昇天できるのか、いまいちピンと来ません。
その当時は101一択と強く思っていました。例え100点差のトップであろうが、そのゲームの勝者なら胸を張って天国に行ける筈だからです。
それから時を経ること17年、ある日土井泰昭氏(協会の初代代表)の事務所に行くと「今度のルール、オカありにするから」と告げられ、筆者は「・・・」と絶句することになります。
オカとはご存知のように、「25000点持ちの30000返し」の差を指す用語で、もともとは1ゲーム毎に20000点分をプールして、遊んだ後にゲーム料金や飲食代に充当していたのでした。
それがなぜか、ゲーム代が各自払い(現在はトップ者から一括徴収に変化)の所謂「フリー麻雀」にそのまま採用され今に至ります。「競技団体がオカあり・・・」と目を丸くしている筆者に対し、「だって世間はみんなそうだよ」と涼しい顔の土井代表。
「ビールと餃子代を取るんですか!」と、毒でも吐いておけば気分も多少はましだったかもしれませんが、「近代麻雀」の編集者を皮切りに売れる雑誌を作ること一筋で仕事をしていた土井氏、また新団体を興し絶対に伸長させる責任を負った代表としては、当然の選択といいたかったに違いありません。
コンセプトは「一般ファンの土俵でプロの技術を見せること」でしたが、今回逢川さんと話してみて、それは脈々と受け継がれていることが確認できました。
実は筆者も古川凱章責任編集時代の「近代麻雀」の編集者です。その当時、麻雀の内容を伝える手段としては、観戦記で概要を伝え、一摸一打をすべて伝えたいときには全体牌譜を使うしかありませんでした。
全体牌譜から対局内容を読み取るためには、相当の熟練度とマニアックな関心が必要だったと思います。今では、動画で簡単に観ることができますし、それをゲームのクライアントに落し込んだ解説動画まで存在します。
「観る雀」を拡げるためには
将棋では自らは指さないが、観戦は大好きという「観る将」と呼ばれるファン層が確立していますが、麻雀はどうでしょうか。将棋は完全情報ゲームなのでプロは自分の持ち時間の範囲でとことん考えて最善手を探します。
そのためにまま1時間を超えるような長考が生じることもありますが、そんなときはやはりプロの解説者や聞き手が、対局者が何を考えているかを推測してファンに伝えているので「観る将」は飽きないのです。
麻雀も読みの技術が深化して、長考が要求される局面もあるようです。ただ、今のルールでは摸打のスピードは任意なので、競技者にとっては不公平、的確な解説がともなわない場合は観戦者にとっての不満につながる恐れがあります。
マージャン競技にとっての大きな課題の一つです。