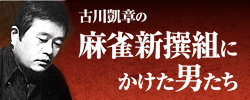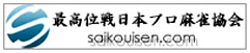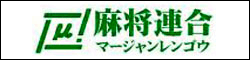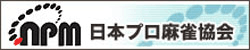五十嵐さんの「麻雀きょうぎ」第2回「断捨離のススメ」を読んで、同じことを37年もやっていると、考えることは似てくるもんだなとつくづく感じました。
どの部分かというと、
もうひとつ、卓上に転がっている邪魔者(?)がありますね。供託棒です。
「えっ、供託棒をなくすってリーチ棒をなくすってこと? リーチはかけられないの?」
と思われるかもしれませんが、いえ、ちがいます。リーチはもちろんかけられます。
ただし、アガった人が貰えるとか、流局したら供託棒として卓上に置かれたままとかにはならない。リーチをかけるときはリーチ料として「支払う」のです。リーチをかけた本人がアガっても戻ってきません。(編集部注:第5期ピンチェリーグはこのルールを採用していた)
具体的には、リーチをかける人がリーチ宣言をし、立会人に千点棒を渡す。あるいはサイドテーブルに置かれた、豚の貯金箱でもなんでもいいですが、簡単に取り出せない専用の箱にポトンと落とし入れればいいのです。保険金の用語で言うなら「掛け捨て」というわけです。
というところです。
注に記しましたが、土田さん主宰のピンチェリーグでは筆者が提案しそれが採用されていました。
供託リーチ棒の影響力
筆者が考えた点は次のようなものです。
リーチ棒を出すことによって局面を変えることができるのは競技としてあまりにも複雑すぎるのではないか。
例えば、このような点棒状況で優勝が決まる最終局を迎えたとします。
1位 40600(東家)
2位 28500(自分)
3位 28400
4位 22500
1位が東家なのでノーテン宣言でゲームを終わらせることができるため、(自分)が優勝するためにはハネ満ツモか64以上の直撃が必要になります。
そんな状況でどうしても満貫手にしかならない(便宜上裏ドラは考慮しない)とき、何か手段はないでしょうか。
実は直撃以外逆転の可能性のない満貫手で先制リーチをかけるという奥の手があります。
供託が1000点出たことによって、3位と4位の条件が緩和され、それぞれ満ツモ、ハネツモ条件になるのです。
狙いは、他2名からのリーチでした。
その結果として自分の条件も緩和して、満貫をツモっての逆転優勝を狙うのです。
現在までのリーチに関するルールの変遷で大きなポイントを記すと、
①リーチ後の暗カンが不可になる
②試合終了時の供託リーチ棒がトップ取りから供託になる
の二つが挙げられるでしょう。
①の理由は、リーチはこれ以上手を変えないことが条件であるのに、暗カンは実質的に手を変化させているというものです。
裏ドラ・一発ありは競技に適しているのか?
この理屈は当然といえば当然で、暗槓を許すと大抵の場合アガリ点も高くなりますし、カンドラや増えた裏ドラの影響で劇的に変わる可能性も出てきます。
これを先ほど話と融合させてみると、こんな打ち方も認められるかもしれません。
3倍満ツモ条件下、ピンフ・イーペーコー(表ドラ2枚かつ4枚使いの牌あり)でリーチをかけ、一発でツモった場合はアガリを宣し、空振りした場合は誰かがカンをしてドラが増えるのを待つ、などです。
ドラ 













もちろん、裏ドラ4枚(一発め以降は8枚)を計算に入れたプレーではありますが、可能性がゼロではない以上、それをあるまじきプレーだと否定することはできません。
仮にリーチ後に新ドラは適用されないというルールを作ったとしても、裏ドラを最大限計算した上に一発ツモしか意味の無いリーチはあり得ます。
問題なのは、相手のプレイの内容(意図)を特定できないことで、それが技を競うという点で大きな妨げになっていると筆者は感じるのです。
このテーマを土田さんにもぶつけてみたのですが、彼は筆者が一瞬たりとも考えたことのないアイデアを語り始めました。冒頭、「考えることは似てくる」と記しましたが、土田さんに限っては、遙か上空を往く発想力と感嘆するしかありません。
それは次週リリースいたしますので、楽しみにお待ちください。